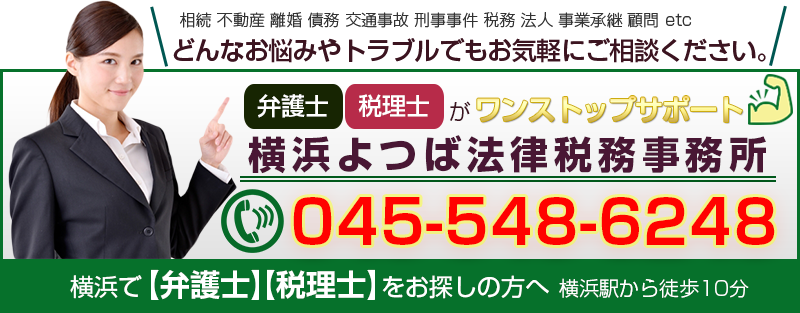再転相続における熟慮期間の起算点
再転相続とは、例えばAさんの相続人であるBさんが、Aさんの相続(第1次相続)について承認または放棄をしないで死亡し、CさんがBさんの相続人となった(第2次相続)場合のことを指します(これに対し、第1次相続を承認したものの、遺産分割未了のまま第2次相続が発生した場合を数次相続と言います。)。
再転相続の場合、Cさんは第1次相続についての承認・放棄の選択権をBさんから承継しますが、Aさんの相続に係るCさんの熟慮期間の起算点についての最高裁の考え方を、ご紹介いたします。
事案について簡単に説明します。BさんはAさんの相続人となったことを知らず、そのためAさんの相続について放棄することなく死亡しました。Cさんは、その頃にBさんの相続人となったことを知りました。それから数年が経過し、CさんはAさんの債権者から請求を受けたことにより、BさんがAさんの相続人であり、自身がAさんの相続人の地位を承継することを知りました。Cさんは、それから3か月以内に相続放棄の申述をしています。
それまでの通説では、第1次相続の熟慮期間の起算点を、Cさんが第2次相続の相続人であることを知った時としていました。通説によると、本件では、CさんがBさんの相続人となったことを知った時から数年経過しておりますので、Aさんの相続について放棄はできないことになります(別の理屈で例外的に放棄を認める余地はありますが。)。
最高裁第二小法廷令和元年8月9日判決は、「民法916条にいう『その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時』とは、相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである。」としました。つまり、第1次相続の熟慮期間の起算点は、Cさんが第1次相続の相続人の地位を自身が承継した事実を知った時としたのです。
先ほど事案では、CさんはAさんの債権者から請求を受けて初めて、第1次相続の相続人の地位を自身が承継したことを知ったので、その時点が熟慮期間の起算点となります。熟慮期間内でありますので、Cさんの相続放棄は認められるという結論になります。
同最高裁判決は、民法916条の趣旨について、再転相続人の第1次相続についての選択の機会を保障する点にあるとしており、係る趣旨からの明快な理屈で妥当な結論を導けるものと言えるのではないでしょうか。